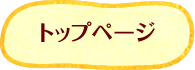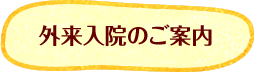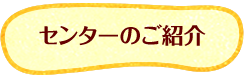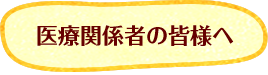埼玉県立 小児医療センター > 各部門の紹介 > 外科系診療部門 > 小児外科
ここから本文です。
掲載日:2025年7月25日
小児外科
小児外科のご紹介
小児外科とは
子供は大人と比較して体が小さいだけでなく、独特な身体的、生理学的特徴を持ち合わせています。子供の特性を考慮して考えられた術式を的確に行う必要があり、そのための技術も重要です。
また、小児は治療後も長期間にわたって日常生活を送ります。そのため治療後の機能にも十分に配慮しなくてはなりません。
私たち埼玉県立小児医療センターの小児外科ではこれらのことを踏まえ、それぞれのお子さんにとって最も適切な治療法を、確実な手技で治療を行うことを心がけております。
対象となる疾患
- 生まれつきの外科疾患、腫瘍、炎症性疾患
- 足の付け根やお臍がとびでている子(鼠径ヘルニア、臍ヘルニア)
- 肛門周囲の炎症やおでき(肛門周囲膿瘍、乳児痔瘻)
- よく吐く子(肥厚性幽門狭窄症、胃食道逆流症)
- 便秘の子(ヒルシュスプルング病、慢性便秘症)
- お腹や胸を痛がる子(急性虫垂炎、腸重積、腸閉塞、膵炎、気胸など)
- 胸に変形のある子(漏斗胸、鳩胸)
- 体が黄色い、便が白い子(胆道閉鎖症、先天性胆道拡張症)
- 食べてはいけないものを誤って食べてしまった子(消化管異物)
- 気管に誤ってものが入ってしまった子(気道異物)
- お腹、胸、首などにしこりを触れる子(良性腫瘍、悪性腫瘍)
- お腹や胸を強く打ってしまった子(外傷)
- 便に血液が混じる子(潰瘍性大腸炎、クローン病、メッケル憩室、大腸ポリープなど)
上記以外でも、外科的な病気のお子さんは全て拝見していますが、一般の外傷、熱傷などには対応しておりません。各疾患に関しての詳細は日本小児外科学会のホームページに解説されています。ご参照ください。
小児外科の特色と当院での新しい取り組み
当センター小児外科では年間、約700例(うち新生児手術が約40例)と全国でも有数の手術数を行っています。これらの中には、鼠経ヘルニアなどの短期入院の小手術が約300件を占めていますが、緊急手術件数も年間約200件程度であり、夜間、休日を問わず患者様の状態により緊急手術も必要に応じて行っております。
また従来は開腹や開胸手術で行われている手術も、当センターでは内視鏡手術を積極的に導入しております。内視鏡手術を行うことで、傷はより小さく整容性に優れ、お子さん達の手術に伴う侵襲を軽減し、術後の早期回復が望めます。当センターには日本内視鏡外科学会技術認定医(小児外科部門:川嶋寛、出家亨一)が在籍しており、内視鏡手術をより安全に、また標準術式とするべく日々努力しております。
内視鏡手術を積極的に行っていますが、それ以外の開腹、開胸手術も多く手掛けております。また悪性腫瘍の児の治療に関しては、血液腫瘍科、放射線科など他科と協力し、お子さんにとって最も適切な治療方針を検討し治療をすすめております。
現在最も多く行っている腹腔鏡下鼠経ヘルニア根治術を説明します。
腹腔鏡下鼠経ヘルニア根治術(SILPEC)
単孔式と呼ばれる術式で、お臍からカメラと鉗子を挿入して手術を行います。術後はお臍の皺に傷が隠れるため、傷がほとんど分からなくなります。当院で開発され、改良が加えられてきたオリジナルの術式であり、年間300件以上の手術を施行しています。


術後3カ月、お臍の皺に傷は隠れてしまい、術創は全くわかりません。
また当センターでは隣接する、さいたま赤十字病院と連携し2019年5月1日より「さいたま新都心医療拠点移植センター」を設立しました。同年10月より小児の生体肝移植を開始し、小児外科医も移植外科と連携し、その手術に携わっています。
詳細は埼玉県立小児医療センター移植外科のホームページをご参照ください。
小児外科へご受診、ご紹介いただくには
当院は紹介病院となっております。初めて当院を受診するには、紹介状が必要となります。
定時の外来診療は、毎週月曜日、火曜日、木曜日に行っております。予約に関しては外来診療日程をご参照ください。長い治療経過ののちにご紹介いただく場合や、現在入院中の患者様の転院などのご相談は、担当の先生を通じて小児外科の医師に直接ご連絡ください。小児外科疾患の多くは緊急疾患であるため、患者さんの状態に合わせて、24時間、365日、休日を問わずいつでも受け入れを行っております。
セカンドオピニオンをご希望の場合は、月曜日午後のセカンドオピニオン外来でお受けしております。
「セカンドオピニオン外来のご案内」のページをご覧ください。
病棟は原則的に付き添いの必要がない基準看護となっています。またお子さん達の状況に合わせて母子が同室で入院できる設備も備えており、少しでも快適な入院生活を行えるよう配慮に努めています。
重症の慢性便秘、遺糞症、便失禁など排便障害のお子さん達の専門外来を保健発達部で行っております。
硬くてコロコロうんちのお子さんが多いので「うさぎ外来」と名付けました。外科外来で初診後、うさぎ外来に移っていただき、浣腸や洗腸の方法を含め排便管理について専門の支援看護師とともに、チーム医療で排便に苦しむお子さん達のご相談にのっております。
小児外科の診療実績
当センターは2016年12月27日に岩槻区馬込より中央区新都心に移転開院を行いました。
移転に際し、新生児集中治療室(NICU)を15床から30床に、新生児治療回復室(GCU)を27床から48床に増床し、小児集中治療室(PICU)も新たに14床新設しました。より多くの病気に苦しむお子さん達に適切な医療を提供できるように日々努力しています。
新病院に移転後、2017年から2019年の3年間に、当センターで実施した主な小児外科疾患の手術実績をお示しします。
表中の括弧内の数字は内視鏡(腹腔鏡や胸腔鏡)を用いて行った手術数です。
入院、手術件数等(2017年から2019年の3年間)
| 入院数 |
2,583件 |
|---|---|
| 手術数 |
2,255件 |
| 内視鏡手術数 |
1,045件 |
主要な手術内訳、件数
| 手術内容 | 件数 |
|---|---|
| 鼠径ヘルニア根治術 |
610(608) |
| 急性虫垂炎に対する虫垂切除術 |
116(116) |
| 臍ヘルニア根治術 |
111(0) |
|
停留精巣固定術 |
94(0) |
| 腸重積症に対する手術による整復 |
7(7) |
| 悪性腫瘍に対する摘出術・生検術 |
51(20) |
| 肥厚性幽門狭窄症手術 |
33(30) |
| 良性腫瘍摘出術 |
57(14) |
| 胃食道逆流症に対する噴門形成術 |
40(40) |
| 鎖肛根治術 |
38(11) |
| イレウス解除術 |
46(10) |
| 腸閉鎖症根治術 |
29(0) |
| 漏斗胸に対する胸骨挙上術 |
3(3) |
| 壊死性腸炎、特発性回腸穿孔 |
12(0) |
| 胆道閉鎖症に対する葛西手術 |
8(0) |
| ヒルシュスプルング病根治術 |
14(13) |
| 喉頭気管分離術 |
17(0) |
| 腸回転異常症に対するラッド手術 |
7(1) |
| 胆道拡張症根治術 |
18(17) |
| 各種肺疾患に対する肺切除術 |
31(30) |
| 臍帯ヘルニア、腹壁破裂根治術 |
6(0) |
| 各種脾疾患に対する脾臓摘出術 |
6(5) |
| 横隔膜ヘルニア根治術 |
10(6) |
| 食道閉鎖症根治術 |
12(6) |
小児外科のスタッフ紹介

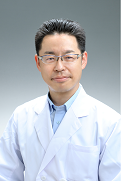
| 名前 | 川嶋 寛 |
|---|---|
| 役職 | 科長 |
| 専門(得意分野) | 小児外科 |
| 資格 |
日本小児外科学会専門医・指導医、日本外科学会専門医、 日本内視鏡外科学会技術認定医(小児外科部門) |
| 最終学歴(卒業年) | 埼玉医科大学医学部(1995年(平成7年)卒) |
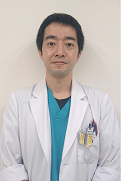
|
名前 |
出家 亨一 |
|---|---|
|
役職 |
医長 |
|
専門(得意分野) |
小児外科学 |
| 資格 |
医学博士、日本小児外科学会専門医・指導医、 日本外科学会専門医・指導医、 がん治療認定医、日本周産期・新生児医学会認定外科医、 日本内視鏡外科学会技術認定医(小児外科部門) |
|
最終学歴(卒業年) |
群馬大学(2007年(平成19年)卒) |

|
名前 |
髙城 翔太郎 |
|---|---|
|
役職 |
医長 |
|
専門(得意分野) |
小児外科学 |
| 資格 |
日本小児外科学会専門医、日本外科学会専門医、臨床研修指導医 |
|
最終学歴(卒業年) |
大分大学(2017年(平成29年)卒) |
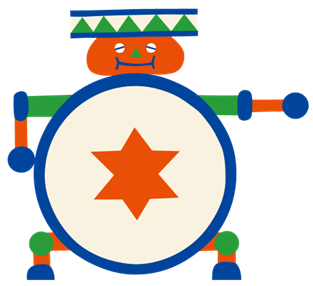
|
名前 |
小川 祥子 |
|---|---|
|
役職 |
医員 |
|
専門(得意分野) |
小児外科学、一般外科学 |
| 資格 |
日本外科学会専門医 |
|
最終学歴(卒業年) |
慶応義塾大学(2016年(平成28年)卒) |

|
名前 |
津坂 翔一 |
|---|---|
|
役職 |
医員 |
|
専門(得意分野) |
小児外科、消化器外科 |
| 資格 | 日本外科学会専門医 |
|
最終学歴(卒業年) |
北海道大学(2018年(平成30年)卒) |
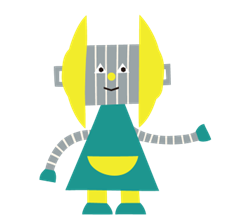
| 名前 | 松田 理奈 |
|---|---|
| 役職 | 医員 |
| 専門(得意分野) | 小児外科 |
| 資格 | 日本外科学会専門医、がん治療認定医 |
| 最終学歴(卒業年) | 山形大学(2018年(平成30年)卒) |
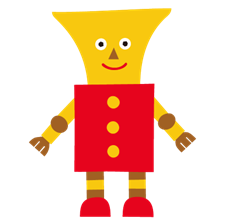
|
名前 |
海老原 統基 |
|---|---|
|
役職 |
医員 |
|
専門(得意分野) |
小児外科学 |
| 資格 | 日本外科学会専門医 |
|
最終学歴(卒業年) |
東京大学(2019年(平成31年)卒) |
外科・移植外科兼任スタッフ紹介

|
名前 |
水田 耕一 |
|---|---|
|
役職 |
移植センター長・移植外科科長・外来統括部長・病院産業医 |
|
専門(得意分野) |
小児肝移植、小児肝胆道疾患 |
| 資格 | 日本外科学会指導医、日本小児外科学会専門医、日本移植学会認定医 |
|
最終学歴(卒業年) |
熊本大学医学部(1991年(平成3年)卒)、東京大学大学院 |
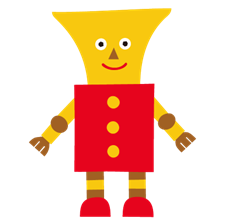
| 名前 | 山田 直也 |
|---|---|
| 役職 | 移植外科医長 |
| 専門(得意分野) | 小児肝移植、消化器・一般外科、肝疾患 |
| 資格 | 日本外科学会認定医、日本消化器外科学会認定医、日本肝臓学会専門医 |
| 最終学歴(卒業年) | 富山大学医学部(2009年(平成21年)卒) 自治医科大学大学院(2020年(令和2年)卒) |
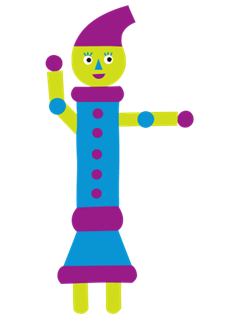
|
名前 |
納屋 樹 |
|---|---|
|
役職 |
移植外科医員 |
|
専門(得意分野) |
消化器、一般外科 |
| 資格 |
日本外科学会専門医 |
|
最終学歴(卒業年) |
自治医科大学(2013年(平成25年)卒) |

|
名前 |
井原 欣幸 |
|---|---|
|
役職 |
移植外科応援医師(外科兼務) |
|
専門(得意分野) |
小児肝移植、小児肝胆膵外科、小腸移植、移植免疫学 |
| 資格 |
日本外科学会認定医・専門医、日本移植学会認定医、 日本小児外科学会専門医、日本肝臓学会専門医、 日本周産期新生児学会認定外科医、日本小児栄養消化器肝臓学会認定医 |
|
最終学歴(卒業年) |
旭川医科大学(1998年(平成10年)卒)、 |
お知らせ
- 埼玉県立小児医療センターは、紹介制です。医療機関の紹介状を必ずお持ちください。
- 受診される方はあらかじめ予約センター(048-601-0489)にお電話いただき予約を取って受診してください。
National Clinical Database
患者さんへ:専門医制度と連携したデータペース事業について
病院医療の崩壊や医師の偏在が叫ばれ、多くの学会や団体が医療再建に向けて新たな提言を行っていますが、どのような場所でどのような医療が行われているかが把握されていない状況では、患者さん目線の良質な医療は提供できません。そこで日本では、関連する多くの臨床学会が連携し、わが国の医療の現状を把握するため、『一般社団法人National Clinical Database』(以下、NCD)を立ち上げ、データベース事業を開始することになりました。この法人における事業を通じて、患者さんにより適切な医療を提供するための専門医の適正配置が検討できるだけでなく、最善の医療を提供するための各臨床現場の取り組みを支援することが可能となります。何卒趣旨をご理解の上、ご協力賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
一般社団法人National Clinical Database 代表理事
里見進
1.本事業への参加について
本事業への参加は、患者さんの自由な意思に基づくものであり、参加されたくない場合は、データ登録を拒否して頂くことができます。なお、登録を拒否されたことで、日常の診療等において患者さんが不利益を被ることは一切ございません。
2.データ登録の目的
患者さんに向けたより良い医療を提供する上では、医療の現状を把握することは重要です。NCDでは、体系的に登録された情報に基づいて、医療の質改善に向けた検討を継続的に行います。NCD参加施設は、日本全国の標準的成績と対比をする中で自施設の特徴と課題を把握し、それぞれが改善に向けた取り組みを行います。国内外の多くの事例では、このような臨床現場主導の改善活動を支援することにより、質の向上に大きな成果を上げています。
3.登録される情報の内容
登録される情報は日常の診療で行われている検査や治療の契機となった診断、手術等の各種治療やその方法等となります。これらの情報は、それ自体で患者さん個人を容易に特定することはできないものですが、患者さんに関わる重要な情報ですので厳重に管理いたします。情報の取り扱いや安全管理にあたっては、関連する法令や取り決め(「個人情報保護法」、「疫学研究の倫理指針」、「臨床研究の倫理指針」、「医療情報システムの安全管理に関するカイドライン」等)を遵守しています。登録されたご自身のデータをご覧になりたい場合は、受診された診療科にお問合せ下さい。
4.登録される情報の使われ方
登録される情報は、参加施設の治療成績向上ならびに皆さまの健康の向上に役立てるために、参加施設ならびに各種臨床領域にフィードバックされます。この際に用いられる情報は集計・分析後の統計情報のみとなりますので、患者さん個人を特定可能な形で、NCDがデータを公表することはー切ありません。情報の公開にあたっても、NCD内の委員会で十分議論し、そこで承認を受けた情報のみが公開の対象となります。
お問合せについては受診された診療科またはNCD事務局までご連絡下さい。
National Clinical Database 事務局
URL:hhttp://www..ncd.or.jp/
(お問合せはホームベージ内のフォームからお願いいたします。)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください