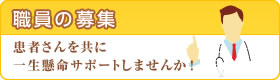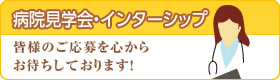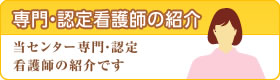循環器・呼吸器病センター > 診療科及び各部門の紹介 > 脳神経センター
ここから本文です。
掲載日:2026年1月26日
脳神経センター
- 日本脳神経外科学会 専門研修プログラム 連携施設
- 日本脳神経血管内治療学会認定研修施設
- 日本脳卒中学会認定研修教育施設は
- 日本脳卒中学会 一次脳卒中センター(PSC)コア施設
- 埼玉ストロークネットワーク(SSN) 基幹施設
脳神経センター特集
リンクをクリックすると各掲載メディアのページへ遷移します。
その他の記事はこちら↓
- 吉川雄一郎医師紹介 脳動脈瘤を得意な領域としている医師を探す(メディカルノート)
- 吉川雄一郎 脳神経センター長の独自取材記事(ホスピタルファイルズ)
- 手術で予防を図る 脳梗塞脳神経センターで行う脳梗塞の予防的治療(ホスピタルファイルズ)
- 脳動脈瘤をはじめとしたさまざまな脳疾患に対する脳神経外科手術(ホスピタルファイルズ)
- 県北部を支える脳疾患治療施設としてくも膜下出血に24時間対応(ホスピタルファイルズ)
外来診療スケジュール(新館棟1階)
|
|
月曜日(午前) |
水曜日(午前) |
金曜日(午前) |
|
|---|---|---|---|---|
|
診察室(6) |
吉川 雄一郎 (初診) |
|
吉川 雄一郎 (初診) |
|
|
診察室(7) |
栢原 智道 |
大塚 俊宏 |
佐藤 政哉 |
|
| 診察室(8) |
埼玉医大医師 |
埼玉医大医師 |
||
- 当院は、紹介制・予約制の医療機関です。初診の方は、紹介状が必要です。かかりつけ医等にご相談いただき紹介状を入手してから、事前の予約(予約専用電話)をお願いいたします。
- 初診の方は、上記スケジュールにかかわらず、原則として11時までに受付してください。
脳神経センターについて
脳卒中は発症からどれだけ急いで治療が開始できるかによって、その予後が大きく変わります。これまで、埼玉県北部地域(秩父を含む)には、24時間体制で高度な脳卒中緊急治療を行うことができる病院が少なく、離れた地域の大病院まで時間をかけて搬送される患者が少なくありませんでした。こうした北部地域における脳卒中医療の現状を改善するために、2019年4月「脳神経センター」が開設されました。現在当センターでは、24時間体制で、開頭手術やカテーテルによる急性期血行再建(血栓回収療法)を行っており、埼玉ストロークネットワーク(SSN)基幹施設、日本脳卒中学会一次脳卒中センターコア施設に認定されています。
脳神経センターでは熊谷、深谷、秩父、比企、本庄・児玉、行田、鴻巣、羽生など埼玉県北部全域の救急隊と緊密な連携をとり、脳卒中高度救急医療を24時間365日、万全の受入体制で提供しています。脳神経センター開設1年間で救急搬送・手術件数ともに飛躍的に増加し、県北地域最大規模の脳卒中センターに成長しました。特に脳動脈瘤や頸動脈狭窄症をはじめとした脳血管障害に対する手術治療数は県内有数で、ハイブリッド手術室や術中ナビゲーションシステムの導入により開頭手術とカテ―テル治療(脳血管内治療)を併用した高難度病変の治療も可能になりました。
我々の扱う疾患は、脳内出血、くも膜下出血、脳動脈瘤、脳血管奇形、脳梗塞といった脳卒中、さらには脳腫瘍、頭部外傷、水頭症、顔面痙攣、三叉神経痛、てんかんまで多岐にわたります。3テスラMRIや128列マルチスライスCT装置、脳血管撮影装置、核医学検査装置など様々な最新の機器を用いた検査により治療方針を決定し最適な治療を提供しています。脳動脈瘤に対しては、開頭手術(クリッピング術)と血管内治療(コイル塞栓術)のいずれの治療が最適かを、また、頸動脈狭窄症に対しても、外科手術(CEA:内膜剥離術)、血管内治療(CAS:頸動脈ステント)のいずれの治療が最適かを、それぞれの症例ごとに十分に検討し、安全確実な治療方法を選択しています。脳血管奇形や高難度動脈瘤などの治療難度の高い疾患に対しては、開頭手術とカテーテル治療をひとつの手術室で同時に行う「ハイブリッド治療」という最新の技術を導入した治療を行うことも可能です。
脳神経センターでは、日本脳神経学会データベース事業(JND)、日本脳卒中学会主導のCOVID-19関連脳卒中に関する研究をはじめ、いくつかの観察研究(非侵襲・非介入研究)を行っています。詳細については当センターホームページ内のオプトアウトによる臨床研究をご覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください