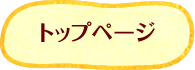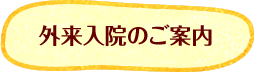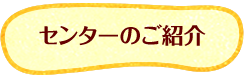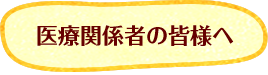埼玉県立 小児医療センター > 各部門の紹介 > 内科系診療部門 > 神経科 > 健康情報/ADHDってなに?
ここから本文です。
掲載日:2025年4月14日
健康情報/ADHDってなに?
ADHDってなに?
「落ち着きがない」、「人の話しをきけない」、「我慢出来ない」、「ずっと動く」等の特徴を示し何度注意されても言う事が聞けない子供がいます。昔は育て方の問題だとか言われていたこともありますが、これらの特徴を有する子供たちの一部はADHDといわれる病気と考えられるようになってきました。
ADHDとはattention deficit hyperactivity disorderの略で注意欠陥多動性障害と訳されます。
むかしはADHD症状を有する子供達に脳障害が生じている証拠がはっきりしないため、検査で見つからない小さな脳の異常によるとして微細脳機能障害(MBD)と呼ばれていたこともあります。その後は注意力の低下に関心が集まり注意不足障害(ADD =attention deficiency [deficit] disorder)と呼ばれていましたが、1980年頃から注意欠陥とともに活動亢進がその定義として考慮されるようになり、アメリカで広く普及している精神神経疾患の診断基準(DSM-IV)が1994年に改訂され,ADHD〔注意欠陥多動性障害〕と呼ばれるようになりました。
ADHDは男児に多く、男児では女児の2倍から3倍の発症率と報告されています。またADHDの60%がLD(学習障害)も呈しているといわれています。ADHDの発症率は日本では詳しいデータがまだないようですがアメリカでは5%、イギリスではおよそ3%だと言われています。
これまでに多くの研究がなされ、ADHDの子供の脳の働きにおいて通常の人と違うことが存在することが分かり、ADHDで脳の異常が存在することとその原因が推測されてきています。しかし、日常診療で使用されるCT、MRIでそれらの原因となる脳の異常を明らかにすることはできていません。ADHDでは通常の検査では異常を認めることがなく、行動観察のみに基づくのみの診断となりますが、大事なことはADHDが親のしつけが悪いために引き起こされるものではなく、病気であるということです。
ADHDの診断
ADHDは7歳未満に発症し【不注意】【多動】【衝動性】という3つの特徴的な行動を必須とする症候群です。不注意とは学業など意識の集中が必要な時に集中ができない状態のことです。多動性とは、動き回ったり、座っていても落着き無くじっとしていられない状態をいいます。衝動性とは考えなしの行動や待たねばならない時に待つことができない状態を示しています。発症年齢とこの3つの症状を持ち、学校(あるいは仕事)や家庭や友人関係などの2つ以上の状況でこれらの症状がみられ(すなわち、家庭でも学校でも症状が認められる)、かつそれが生活上における障害となっている時にADHDと診断されます。また下記に述べるようにDSM-IVの基準では、広汎性発達障害、自閉症、気分障害(躁うつ病、うつ病など)や分裂病あるいは心因反応などがある場合は、その診断を優先することになっています。少し難しいかもしれませんが先ほどの述べたアメリカで普及しているの診断基準DSM-4の一部を訳したものをお示しします。
1.以下の(1)、(2)のどちらか
(1) 以下の不注意の症状のうち6つ(またはそれ以上)が少なくとも6ヶ月以上続いていたことがあり、その程度は不適応的で、発達の水準に相応しないもの。
【不注意】
- 学業、仕事、またはその他の活動において、しばしば綿密に注意する事が出来ない。または、不注意な過ちをおかす。
- 課題または遊びの活動で注意を持続する事がしばしば困難である。
- 直接話し掛けられた時にしばしば聞いていないように見える。
- しばしば指示に従えず、学業、用事、または職場での業務をやり遂げる事ができない(反抗的な行動または指示を理解できないためではなく)。
- 課題や活動を順序立てる事がしばしば困難である。
- (学業や宿題のような)精神的努力の持続を要する課題に従事することをしばしば避ける、嫌う、またはいやいや行う。
- (例えば、おもちゃ、学校の宿題、鉛筆、本、道具など)課題や活動に必要なものをしばしばなくす。
- しばしば外からの刺激によって容易に注意をそらされる。
- しばしば毎日の活動を忘れてしまう
(2) 以下の多動性-衝動性の症状のうち6つ(またはそれ以上)が少なくとも6ヶ月以上持続したことがあり、その程度は不適応的で、発達の水準に相応しない。
【多動性】
- しばしば手足をそわそわと動かし、またはいすの上でもじもじする。
- しばしば教室や、その他、座っていることを要求される状況で席を離れる。
- しばしば不適切な状況で、余計に走り回ったり高い所へ上がったりする(青年又は成人では落ち着かない感じの自覚のみに限られるかもしれない)。
- しばしば静かに遊んだり余暇活動につくことができない。
- しばしば"じっとしていない"または"まるでエンジンで動かされてるように"行動する。
- しばしばしゃべりすぎる。
【衝動性】
- しばしば質問が終わる前に出し抜けに答えてしまう。
- しばしば順番を待つ事が困難である。
- しばしば他人を妨害し、邪魔する(例えば,会話やゲームに干渉する)。
2. 多動性-衝動性または不注意の症状のいくつかが7歳未満に存在し、障害を引き起こしている。
3. これらの症状による障害が2つ以上の状況において(例えば、学校〔または仕事〕と家庭)存在する。
4. 社会的、学業的または職業的機能において、臨床的に著しい障害が存在する明確な証拠が存在しなければならない。
5. その症状は広汎性発達障害、精神分裂病、またはその他の精神病性障害の経過中のみ起こるものではなく、他の精神疾患(例えば、気分障害、不安障害、解離性障害、または人格障害)ではうまく説明されない。
なお、また、この【不注意】【多動】【衝動性】という3つの症状の程度により「混合型」「不注意優勢型」「多動性-衝動性優勢型」の3つに分けられます。
ADHDの原因
専門家や研究者たちの努力で「ADHDが環境によるものではなく器質的原因によるもの」とする多くの証拠が発見されています。それらより、ADHDは脳の中に器質的(体の構造面もしくは機能の面)な発達障害があってそれによって脳内化学物質の分泌と伝達が偏り、不注意、他動、衝動性といった症状を呈すると推測されています。中枢神経興奮剤がADHDに特異的に有効であることから、カテコールアミン系の脳内伝達物質であるドーパミンないしはノルアドレナリンの低活性によるものではないかと推測されています。またセロトニンの機能の障害も指摘されています。
ADHDの治療
中枢神経興奮剤の「塩酸メチルフェニデート」のリタリン(商品名)が有効とされています。覚醒作用があり、一時的に多動を抑制して集中力を高める効果があります。副作用としては、食欲不振、高血圧等の他に神経症状として興奮、チック、舞踏病様症状、Tourette症候群、ジスキネジア等の不随意運動、けいれん等の報告があります。そのためチック、Tourette症候群の既往、興奮性のある患者は禁忌とされています。また、6歳未満の小児では安全性が確立してないという理由で原則禁忌という扱いになっています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください