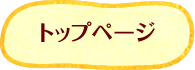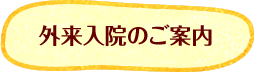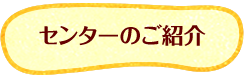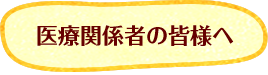埼玉県立 小児医療センター > 各部門の紹介 > 内科系診療部門 > 感染免疫・アレルギー科
ここから本文です。
掲載日:2025年10月21日
感染免疫・アレルギー科
感染免疫・アレルギー科のご紹介
感染免疫・アレルギー科とは
感染免疫・アレルギー科は、日本アレルギー学会、日本リウマチ学会の教育施設に認定されており、感染症・免疫疾患・アレルギー疾患などを対象とし、幅広く、かつきめの細かい診療を行う科です。
入院診療はもちろん、外来診療でもこれらの患者さんの診療を行っています。そのほか、予防接種、院内感染対策も行っています。
当科では次のような症状のお⼦さんの診断や治療をしています。
- 重症な感染症(細菌・ウイルス・真菌・その他)
- 発熱を繰り返しやすい
- 抵抗力が弱い
- リウマチ、膠原病、川崎病
- 重い喘息や⾷物アレルギー
感染免疫・アレルギー科の特徴
感染免疫・アレルギー科では、細菌やウイルスによって引き起こされる感染症を治療するとともに、遺伝⼦技術を使って原因のはっきりしない十種類以上の感染性疾患を迅速に診断しています。既に抗菌剤が投与されているために培養で起炎菌を確定できない重症細菌感染症においてもTm mapping法により、起炎菌が迅速に同定できるようになりました。
当センターでは他科の患者さんも多く入院されていますが、重症で長期入院される関係で、院内感染をうまく防ぐことが極めて重要です。このため、当科を中心に感染対策チームをつくっています。また、他科からの感染症治療のコンサルテーションを受けることも多いです。
生まれつき免疫力が弱いために感染症を繰り返す病気(免疫不全症)の診断と治療もしています。
リウマチ膠原病、自己免疫疾患や自己炎症疾患も当科の対象疾患で、100症例を超える若年性関節リウマチの治療を行っています。
さらに、気管支喘息や食物アレルギーなどのアレルギー性疾患の診断と治療を行っています。
生物製剤と対象疾患
- 【レミケード】若年性特発性関節炎・大動脈炎症候群・川崎病・ベーチェット病
- 【アクテムラ】若年性特発性関節炎・大動脈炎症候群
- 【エンブレル】若年性特発性関節炎・乾癬性関節炎
- 【ヒュミラ】若年性特発性関節炎・乾癬性関節炎
- 【シンポニ】若年性特発性関節炎
- 【リツキサン】若年性皮膚筋炎・慢性活動性EBウイルス感染症・多発血管炎性肉芽腫症
- 【オレンシア】関節リウマチ
- 【シムジア】関節リウマチ
- 【イラリス】クリオピリン関連周期性症候群
- 【ゾレア】気管支喘息
感染免疫・アレルギー科の診療実績
令和6年度の延べ外来患者数は5,782名、外来新患は253名、延べ入院患者数は580名でした。
入院患者は、感染症、リウマチ・膠原病、自己炎症性疾患、免疫不全症、川崎病などです。
リウマチ性疾患においては若年性特発性関節炎、全身性エリテマトーデス、乾癬性関節炎、大動脈炎症症候群、ベーチェット病、ANCA関連血管炎などの疾患においても生物製剤を用いた治療法が行われるようになりました。インフリキシマブ、エタネルセプト、ゴリムマブ、トシリズマブ、アダリムマブ、カナキヌマブ、リツキシマブ、アバタセプトなどが使用されています。疾患によってはステロイドパルス療法、ガンマグロブリン大量療法も積極的に行っています。薬物療法で治療効果不十分の重症例においては、腎臓科の協力のもと、積極的に血漿交換・白血球除去療法を行っています。
また、ステロイド剤は言うまでもなく、メトトレキサート、アザチオプリン、ミコフェノール酸モフェチル、ミゾリビン、シクロホスファミド、シクロスポリン、タクロリムスなどの免疫抑制剤も多くの患者において使用し、良好な結果を得ています。これらの薬剤をうまく組み合わせることにより、ステロイドの副作用を最小限度にとどめることが可能となっており、患者のQOL向上に貢献しています。
埼玉県においては小児のリウマチ疾患を系統的に診療している施設は他になく、県下全域から患者紹介を受けています。
また、近年小児期発症のリウマチ膠原病、免疫不全を持つ成人の患者さんが増えています。当センターの埼玉県移行期医療センターの支援を受けながら、成人病院への移行にも力をいれています。
川崎病については、他院で通常の治療にもかかわらず状態の改善しない重症度の高い症例を多く受け入れ、ステロイドやシクロスポリンに加え、生物学的製剤(レミケード)の併用も行っており、冠動脈病変の発生を未然に防いでいます。また、循環器科と緊密な連携を保ちながら高度な医療を積極的に行っています。
周期性発熱を呈する自己炎症症候群においては、遺伝科との連携で、家族性地中海熱、高IgD症候群(メバロン酸キナーゼ欠損症)、TNF受容体関連周期性症候群(TRAPS)、クリオピリン関連周期性発熱症候群の責任遺伝子診断もできるようになっています。他院にて診断できない症例を的確に診断することにおいて地域医療に貢献しています。
原発性免疫不全症のいくつかの疾患においても、PCR法、アレイ比較ゲノムハイブリダイゼーション(aCGH)法を使用して診断可能となっています。X連鎖性無γグロブリン血症、慢性肉芽腫症の患者を、入院および通院にて治療しています。当科は埼玉県下で、原発性免疫不全症の診断・治療が行える数少ない施設のひとつとなっています。
感染症も多く、肺炎・気管支炎、中耳炎・副鼻腔炎、蜂窩織炎、ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群、リンパ節炎、敗血症・感染性心内膜炎、抗酸菌感染症、咽後膿瘍、細菌性腸炎、腎盂腎炎等の細菌・マイコプラスマ感染症等細菌感染症、アデノ・RS・EB・サイトメガロウイルス感染症、流行性耳下腺炎・水痘ウイルス感染症、ウイルス性気管支炎・肺炎、ウイルス性胃腸炎、ウイルス性髄膜炎、慢性活動性EBウイルス感染症、ウイルス関連血球貪食症候群等ウイルス感染症などが挙げられます。慢性活動性EBウイルス感染症においても生物製剤(リツキサン)を用いた治療法を行っています。先天性サイトメガロウイルス感染症においては、難聴・中枢神経障害に対し、積極的に薬物療法を行っていますが、これは日本では数少ない施設のひとつです。また既に抗菌剤が投与されているために培養で起炎菌を確定できない重症細菌感染症においてもTm mapping法により、起炎菌が迅速に同定できるようになりました。髄膜炎菌感染症の重症例ではこの方法により早期診断が可能となり救命につながりました。また病棟の肝炎対策も迅速にとることができました。
EBウイルスやサイトメガロウイルスなどのウイルス疾患において、リアルタイムPCR法で原因ウイルスの検出とウイルス量の測定を同時に行い診断と病態を解明しています。免疫抑制剤を用いた治療を行っている患児においては日和見感染をおこすことが多いですが、ウイルス定量検査を日常診療の指標とすることができ、的確な免疫抑制剤の使用と抗ウイルス剤の迅速な対応に役立ち、患者予後の改善につながっています。これは当科以外の他科の患者においてもあてはまります。それ以外にも、HHV-6・HHV-7・HHV-8・HSV-1・HSV-2・パルボB19・VZVの定量もできるため、これらを用いた臨床への応用も行っています。これは当科のみならず他科のウイルス感染症の診断にも大いに貢献しています。
アレルギー疾患においても、気管支喘息で生物製剤(ゾレア)を用いた治療を行っています。また、食物アレルギーの診断・治療のため、食物負荷試験を行っています。
感染免疫・アレルギー科のスタッフ紹介

| 氏名 | 菅沼 栄介 |
|---|---|
| 役職 | 科長兼副部長 |
| 資格 |
日本小児科学会専門医、認定小児科指導医、 インフェクションコントロールドクター(ICD)、 日本小児感染症学会小児感染症専門医・指導医 |
| 最終学歴(卒業年) |
東海大学医学部(1999年(平成11年)卒) |
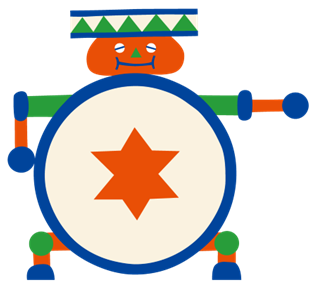
| 氏名 | 佐藤 智 |
|---|---|
| 役職 | 医長 |
| 資格 |
日本小児科学会専門医、日本リウマチ学会専門医・指導医、 日本アレルギー学会専門医・指導医 |
| 最終学歴(卒業年) |
東京医科大学(2000年(平成12年)卒) |

| 氏名 | 上島 洋二 |
|---|---|
| 役職 | 医長 |
| 資格 |
日本小児科学会専門医、認定小児科指導医、 インフェクションコントロールドクター(ICD)、 日本臨床免疫学会免疫療法認定医、日本リウマチ学会専門医・指導医、 医療クオリティマネージャー |
| 最終学歴(卒業年) |
関西医科大学医学部(2006年(平成18年)卒) |
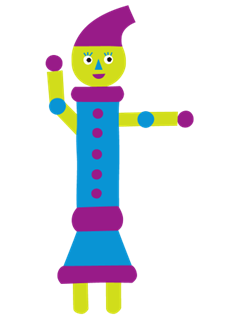
| 氏名 | 古市 美穂子 |
|---|---|
| 役職 | 医長 |
| 資格 |
日本小児科学会専門医、認定小児科指導医、 インフェクションコントロールドクター(ICD)、 日本小児感染症学会暫定指導医、日本小児感染症学会認定医 |
| 最終学歴(卒業年) |
聖マリアンナ医科大学(2008年(平成20年)卒) |

| 氏名 | 真保 麻実 |
|---|---|
| 役職 | 医長 |
| 資格 |
日本小児科学会専門医、日本リウマチ学会専門医 |
| 最終学歴(卒業年) |
群馬大学医学部医学科(2013年(平成25年)卒) |
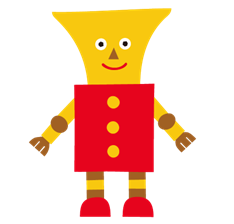
| 氏名 | 谷 柚衣子 |
|---|---|
| 役職 | 医員 |
| 資格 | 日本小児科学会専門医 |
| 最終学歴(卒業年) | 順天堂大学医学部(2016年(平成28年)卒) |
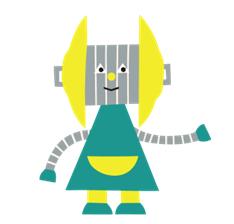
| 氏名 | 大石 勉 |
|---|---|
| 役職 | 非常勤 |
| 資格 |
日本小児科学会専門医、日本リウマチ学会専門医・指導医、 インフェクションコントロールドクター(ICD)、日本感染症学会専門医 |
| 最終学歴(卒業年) |
北海道大学医学部(1973年(昭和48年)卒) |
お知らせ
- HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)接種のご案内
- サイトメガロウイルス外来を開設しました。(令和3年11月)(PDF:952KB)
- リウマチ膠原病外来を開設しました。(令和3年4月)(PDF:771KB)
- 埼玉県立小児医療センターは、紹介制です。医療機関の紹介状を必ずお持ちください。
- 受診される方はあらかじめ予約センター(048-601-0489)にお電話いただき予約を取って受診してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください