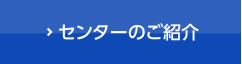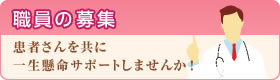ここから本文です。
掲載日:2025年10月10日
埼玉県立精神医療センター精神科専門医研修プログラム
目次
専門研修の理念と使命
理念
精神科領域専門医制度は、精神医学および精神科医療の進歩に応じて、精神科医の態度・技能・知識を高め、すぐれた精神科専門医を育成し、生涯にわたる相互研鑽を図ることにより精神科医療、精神保健の向上と社会福祉に貢献し、もって国民の信頼にこたえることを理念とする。
使命
患者の人権を尊重し、精神・身体・社会・倫理の各面を総合的に考慮して診断・治療する態度を涵養し、近接領域の診療科や医療スタッフと協力して国民に良質で安全で安心できる精神医療を提供することを使命とする。
プログラムの特徴
基幹施設である埼玉県立精神医療センターは、精神科救急病棟(スーパー救急病棟)、精神科急性期病棟、依存症病棟、児童思春期病棟、医療観察法病棟を有し、急性期から地域定着、児童から高齢者、任意入院から措置入院・医療観察法による医療まで症例は豊富で、様々な精神科専門医療まで経験することができる。多職種チーム医療が中心であり、修正型電気けいれん療法、クロザピン、訪問看護等も行っている。
専攻医は、入院患者の主治医となり、指導医からマンツーマンで指導を受けながら、適格な診断と治療の過程を学習する。県立病院ならではのマンパワーに基づく多職種チームの一員となり、多職種の評価を受けながら研修することが可能である。
教育研究面では、倫理・安全管理・感染対策等の院内研修が充実しており、医師としての基本的診察能力(コアコンピテンシー)を高めることができる。臨床や研究の分野に関して自身の関心の領域のものから話題を選んで発表をする場もある。
研修連携施設は、大学病院5、都立病院2、民間病院1である。大学病院ならではの症例や教育・研究、総合病院におけるコンサルテーション・リエゾン精神医学や外来診療、民間病院での地域移行支援等幅広く学ぶことができる。
基幹施設と連携施設における研修で、精神科専門医として必要かつ十分な研修が可能である。本制度における精神科領域専門医の使命である「患者の人権を尊重し、精神・身体・社会・倫理の各面を総合的に考慮して診断・治療する態度を涵養し、近接領域の診療科や医療スタッフと協力して、国民に良質で安全で安心できる精神医療を提供する」専門医を育成することができる。
施設概要
公的単科精神科病院として高度専門医療を提供している。病棟は全て閉鎖であり、精神科救急病棟(スーパー救急病棟)50床、依存症病棟40床、児童思春期病棟30床、精神科急性期病棟30床、医療観察法病棟33床の計183床で、外来は一般精神科外来から専門外来まで幅広く行っている。
疾患としては特に、精神作用物質使用による精神および行動の障害(F1)、統合失調症(F2)、心理的発達の障害(F8)、小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害(F9)が症例豊富である。急性期を中心に、児童から高齢者、任意入院から措置入院・医療観察法対象者、地域医療から高度専門医療まで、精神科医療全般を網羅している。
多職種チーム医療が基本であり、入院初期から退院後の生活を見据えた濃厚な対応を行い、早期社会復帰を目指している。外来では訪問看護も行っている。
スーパー救急病棟は、埼玉県精神科救急情報センターと連携を取り、夜間休日を中心に措置入院等を受け入れている。クロザピンの導入も積極的に行い、地域の医療機関では処遇困難な患者の診療も行っている。
依存症については、アルコール依存症のみならず薬物依存症の入院治療を行っている本邦でも数少ない病棟を有している。外来と連携し、治療の動機付け・集団プログラム・疾病教育等、断酒・断薬の継続のための様々なアプローチをしている。外来では、認知行動療法に基づいた当院独自の薬物再乱用防止プログラム「LIFE(ライフ)」を行っている。近年ではギャンプル依存やゲーム障害など幅広い依存の問題を扱っている。
児童思春期病棟は小学生から入院対応を行い、精神科では県内で唯一の院内学級を併設している。外来も含め、教育・福祉等の関係機関と連携を取りながら、個別指導・集団療法等をチームで行っている。
急性期病棟は、地域からのmECT依頼、結核(結核患者収容モデル事業)や新興感染症を合併する患者の治療、地域での困難事例など幅広い受入を行っている。
応募について
応募資格
日本の医師免許取得後、初期研修を終了し、精神科専門研修を志す者
期間
3年間
専攻医の募集人数
4人
プログラム担当者
氏名:黒木 規臣
住所:〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 818-2
電話番号:048-723-1111
FAX:048-723-1550
E-mail: psychiatry_apply◆saitama-pho.jp(◆を@に変えてお送りください)
応募方法
履歴書等を下記宛先に送付の上、面接申し込みを行う。
〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 818-2
地方独立行政法人埼玉県立病院機構 埼玉県立精神医療センター 総務・人事担当
採用判定方法
履歴書等の記載内容と面接結果に基づき厳正な審査を行い、採用の適否を判断する。
プログラムのまとめ
プログラム詳細一括ファイル(申請中)(PDF:1,134KB)
各施設の概要および診療実績
基幹施設
- 埼玉県立精神医療センター
連携施設
- 埼玉医科大学病院(PDF:343KB)
- 埼玉医科大学総合医療センター(PDF:231KB)
- 東京科学大学病院(PDF:460KB)
- 東京医科大学病院(PDF:253KB)
- 東京大学医学部附属病院(PDF:244KB)
- 東京都立松沢病院(PDF:122KB)
- 東京都立墨東病院(PDF:124KB)
- 成増厚生病院(PDF:222KB)