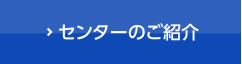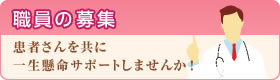ここから本文です。
掲載日:2025年1月31日
子どものこころの健康を支えるために
はじめに
子どもの心身の成長において、こころの健康は非常に大きな要素を占めています。子どもたちが健やかに育ち、幸せな生活を送るために、こころの健康を支えることは必要不可欠です。子どものこころの健康を支えていく方法をお示しします。
<予防編>基本的なこころの健康をサポートするための考え方
1.こころの健康の理解
子どもたちのこころの健康は、からだの健康と同じくらい重要です。ストレス、心配、恐怖、悲しみなど、さまざまな感情が子どもたちのこころに影響を与えます。親や教師、地域社会の皆さんが子どもたちのこころの状態に敏感であることが大切です。
2.コミュニケーションの大切さ
子どもたちは、自分の気持ちを上手に言葉で表現できないことがあります。日常の会話を通じて、子どもたちが安心して気持ちを話せる環境を作りましょう。聞き役に徹し、否定せずに受け入れる姿勢が大切です。
3.適切なサポート体制
こころの健康に問題を抱える子どもたちには、より専門的なサポートが有用な場合があります。学校のカウンセラーや心理士と連携し、適切な支援を提供することで、子どもたちのこころの負担を軽減することができます。
4.ストレス管理
リラクゼーションや深呼吸、適度な運動、趣味の活動など、ストレスを軽減する方法を子どもたちに教えましょう。これらの方法を実践することで、子どもたちは自分でこころの健康を維持するスキルを身につけることができます。
5.愛情と安心感の保証
子どもたちは、愛情と安心を感じることでこころが安定します。家族や周囲の大人たちが愛情をもって接することで、子どもたちは自信を持ち、健やかに成長します。
これらのようなサポートがあったとしても、こころのバランスが崩れることは誰にでもありうることです。より早期に介入と支援を行う観点で、崩れ始めたこころのバランスに対するさらなるサポートに関してお示しします。
<早期介入編>こころのバランスが崩れていくサインを見逃さないために必要な視点
1.行動の変化を観察する
子どもたちの行動に急な変化が見られる場合、それはこころの問題を示しているかもしれません。特に必要なサインとして、学業成績の急激な低下、孤立といった友達関係の変化、普段楽しんでいた活動に対する興味の喪失、過度な反抗な攻撃的な言動、などが例として挙げられます。
2.感情の変化を見逃さない
子どもたちは、自分の感情を言葉で表現するのが難しいことがあります。こころのバランスが崩れるサインとして、過度な不安や緊張、悲しみや絶望感、急ないら立ちや怒り、無気力や疲労感などがあります。変化に注意して気を配れるとよいでしょう。
3.身体変化のサインに注意を払う
こころの問題は身体の症状として現れることがあります。頻繁な頭痛や腹痛といった痛み、過食や拒食といった食欲の変化、体重の急激な変化、過眠や不眠といった睡眠の問題などに注意しましょう。
4.安全な環境を提供する
子どもたちが安心して過ごせる環境を整えることも大切です。家庭や学校での安定した生活環境が、子どものこころの健康に大きく影響します。
5.専門家の助けを求める
子どもがこころの問題を抱えている場合、専門家の助けを求めることが重要です。学校のカウンセラーや心理士、児童相談所、医師などの子どものこころの専門家などに相談し、適切なサポートを受けるようにしましょう。どんな小さなこころの問題であっても、問題が大きくなる前に専門家に相談することで客観的な判断を受けることができます。
子どもたちのこころのバランスが崩れていくとき、社会的な大きな問題に発展し、親や教師、地域の支援者が適切なサポートを提供することが必要です。しかし、時として早期介入と支援だけではなく、医師などの専門職による治療が必要になることがあります。専門的な治療や支援を受ける必要がないこともありますが、専門家に客観的な判断を受けることで、この先にどのようなことに注意して見守ればよいかわかることもでき、安心して支えることができるようになります。
<専門的介入編>早急に専門家に相談を要するサイン
1.持続する感情の不安定や深刻な行動上の変化(長期間の不登校や家庭内暴力など)
2.繰り返される長期間の身体症状の訴え
3.自傷行為や自殺の兆候
4.持続する昼夜逆転などの睡眠の乱れ
5.薬物の過量服薬やアルコール乱用、ゲームやネットへの過剰な没入といった嗜癖行動
6.心的外傷の兆候(フラッシュバックや過覚醒、悪夢体験、記憶の欠落など)
このようなサインがあった際には、早急に専門家に相談しましょう。
子どものこころの専門医から
これらの予防や介入のためのサインを感じ取ったとき、またはこのようなサインが繰り返されたときに、すぐにその意味や理由を子どもに問うのではなく立ち止まって考えてみてほしいことがあります。まずはなぜ子どもがそう思ったのか、そう感じたのか、そのように行動したのかを想像してみてください。話しかけるときは批判しすぎず、ふとそのような想像があっているか聞いてみることも大事なポイントです。子どもたちは、自身に何か変化を感じた時に、自分のことを直接言われると大きく戸惑って、素直な気持ちや感情を示せなくなることがほとんどです。そのようなときにかかわりやすい表現として「私はあなたが○○と思っている(感じている)と思うけれどもどう思う?」などの客観的な声掛けが有効なことがあります。子どもを主語にして決めつけず、どのような子どもたちの言動であっても、あくまで周りの大人は子どもたちのことを心配していると伝えてあげることを大事にしましょう。
私たちは、すべての子どもたちが健やかな心を持ち、明るい未来を築くことを願っています。子どものこころの専門職でないとできないこともありますが、子どものこころの専門職だけでは子どものこころの健康を支えることはできません。そのために、地域社会全体で子どもたちのこころの健康を支えましょう。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください