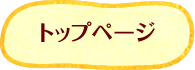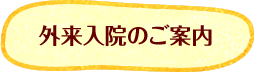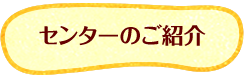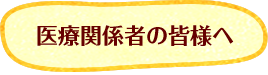埼玉県立 小児医療センター > 各部門の紹介 > 保健発達部門 > 言語聴覚療法(ST)
ここから本文です。
掲載日:2024年10月7日
言語聴覚療法(ST)
言語聴覚療法のご紹介
- 言語聴覚療法とは?
- こんなお子さんが対象です
- 専門外来と個別外来
- 来院されるまでにご家庭に心掛けていただきたいこと
- 言語聴覚療法を受けるには?
- お知らせ:口唇口蓋裂患者様・ご家族向け集団外来「kuchi-com(くちこみ)」のご案内
言語聴覚療法とは?
当センターでは、ことば・きこえ・食べることに障害(心配)のあるお子さんに対して、言語聴覚士(ST)が評価・助言を行います。
→言語聴覚士とは?説明資料(1)(PDF:531KB)・説明資料(2)(PDF:117KB)
こんなお子さんが対象です
当センターでは、以下のような症状をもつお子さんを言語聴覚療法の対象としています。
【ことば】

- 言語発達遅滞
ことばが出てこない、ことばを理解していない。 - 構音障害
発音がはっきりしない、赤ちゃんことばが治らない、カ行がタ行になる等。
または、口蓋裂、舌小帯短縮症による発音の異常。 - 吃音
ことばの最初を繰り返す、引き延ばす、または、つまって声が出ない。 - 学習障害(LD)
学習において、特定分野(読む・書く・聞く・計算)が努力不足では説明できないほど困難を伴う。 - 小児失語症
脳血管障害や脳炎後の後遺症による失語症
【きこえ】

- 難聴
呼びかけや物音に反応しない。聞き返しが多い。 - 補聴器
補聴器の調整、装用指導をしてほしい。
【食べる】
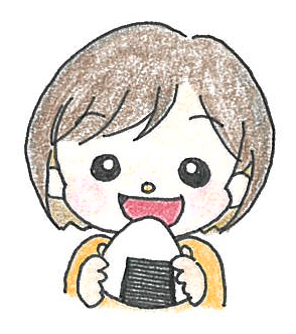
- 摂食・嚥下障害
よく噛んで食べられない。丸呑みしてしまう。ムセ込む。
専門外来と個別外来
当センターでは、上記のような症状のあるお子さんに対する言語聴覚療法として、日時が定められている以下の専門外来を設けています。
専門外来
発音外来
口唇口蓋裂など口腔内疾患のあるお子さんを対象として、発音に関する定期的な評価と助言をしています。
補聴器外来
補聴器の調整と装用指導、療育・教育についての情報提供をしています。
難聴ベビー外来
生後間もない時期に難聴の診断を受けたお子さんやそのご家族を対象とした、音楽療法や講義などによる早期療育プログラムです。
ことり外来
気管切開をしているお子さんを対象に、スピーチバルブの装用指導を通して発声を促したり、代替手段を検討することにより、コミュニケーション力を伸ばす関わり方を指導しています。
個別外来
当センターは三次医療機関であるため、言語聴覚療法においても医療的ケアを必要とするお子さんを基本的な対象としています。ただし、お住まいの地域の医療・療育機関では対応が困難な場合に限り、上記の専門外来以外にも個別の評価・助言を行っています。ご希望の場合は、担当主治医にご相談ください。
(言語療法室のようす)


来院されるまでにご家庭で心掛けていただきたいこと
ことばが増えない、お話がなかなか出来ない場合
お子さんが興味・関心を示しているものについてのことば掛け
お子さんのことばの発達がゆっくりだと、つい一方的に「これはリンゴ」とことばを覚えさせたり、「これは何?」と物の名前を聞いてしまいがちです。そうではなく、お子さんの見ているものや遊んでいるもの、指をさしているものについて、お子さんが言いたいであろうことを代弁するようなイメージで簡単なことば掛けをしてあげましょう。また、お子さんが車を指さして「ぶーぶー」と伝えてくれたら、「ぶーぶー速いねぇ」というように、お子さんのことば“プラス1語”を返してあげましょう。
発音の間違いがある、吃る場合
言い直しはさせずコミュニケーションそのものを楽しむ
誤った発音や吃りながらのお話しであったとしても言い直しはさせないでください。発音の誤りや吃りのあるなしに関わらず、コミュニケーションそのものを楽しみましょう。最後までお話を聞き、その伝えたい内容に注意を向けてあげましょう。少し大きくなって、「くつ」を「くちゅ」というように赤ちゃん言葉が抜けない場合は、それを訂正するのではなく、「くつだね」とさりげなく正しい発音を聞かせてあげましょう。また、吃音は慌てているために生じるものではないので、「ゆっくり」や「落ち着いて」という声掛けも避けましょう。
新生児聴覚スクリーニングでリファー(要再検査・要精密検査)となった場合
子育ての基本は、どんなお子さんでも同じです
赤ちゃんの欲求を満足させ、快い気持ちにさせましょう。赤ちゃんが泣いたら、「どうしたの?」「おなかがすいたの?」等と話しかけ、その時の欲求に応えながら「すっきりしたね」「もうおなかいっぱいになったかな」等、一人二役で話しましょう。同時に、抱っこしたり、ほおずりしたり等のスキンシップをたくさんして快い気持ちを体験させましょう。
通じたという体験をたくさんさせてあげましょう
赤ちゃんは、2ヶ月頃になるとになると、母親のいろいろな働きかけ(話しかけ・抱っこ・あやす・見る・ベビーサイン等々)に、じーっと見返したり、「アー」とか「クック」とか、まるでお話するように声を出したりします。そんな時、目と目を合わせて、赤ちゃん同じように声を出したりして、「分かったよ」ということを伝えてあげましょう。そして、お母さんがそんな赤ちゃんを見て感じた気持ち(かわいさ・喜び等)を自分らしい表現(例えば、キスをしたり、ほおずる等)をふんだんに使って、赤ちゃんに示しましょう。親子の心の安定がコミュニケーション発達の土台となります。
言語聴覚療法を受けるには?
初めて当センターを受診される方
お子さんの症状に応じて、下記の外来への紹介状が必要です。紹介状は一般病院または保健センターの医師から出してもらうことが出来ます。
- 発達外来
- 耳鼻咽喉科外来
- 形成外科外来
- 神経科外来
- 精神保健外来
- 遺伝科外来
すでに当センターの上記の診療科を受診されている方
診察時に医師にご相談ください。
お知らせ
当センターにて口唇口蓋裂治療をされている患者さんとそのご家族を対象に、口唇口蓋裂に対する知識を深めるための情報提供と、患者さん同士の交流を目的としたプログラム「Kuchi-com(くちこみ)」を実施しています。
詳しい内容は、口唇口蓋裂患者様・ご家族向け集団外来「Kuchi-com(くちこみ)」のご案内のページをご覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください