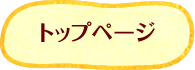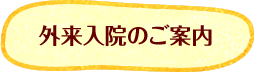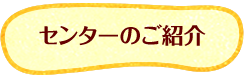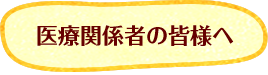埼玉県立 小児医療センター > 各部門の紹介 > 薬剤部 > 業務内容
ここから本文です。
掲載日:2025年7月31日
業務内容
- 薬剤部の組織
- 調剤業務
- 注射薬業務
- 無菌製剤業務
- 医薬品情報業務
- 試験検査業務
- 病棟薬剤業務・薬剤管理指導業務
- チーム医療
- その他の業務(実務実習、他施設や地域との連携)
- 薬剤部のお仕事紹介(YouTube動画)について
薬剤部の組織
薬剤部の最新の基本データは以下をご覧ください。
薬剤部の業務
- マネージメント担当(部長・副部長・副技師長)
- 中央薬剤業務担当
| 調剤担当 | 入院・外来調剤、持参薬管理、薬剤管理指導 |
| 注射担当 | 患者毎1施用単位での供給、請求による供給 |
| 製剤担当 | 中心静脈栄養輸液・抗がん剤の無菌製剤処理、院内製剤 |
| 薬品管理担当 | 発注、在庫管理 |
| 試験検査担当 | 投与設計、院内測定 |
| 医薬品情報担当 | 情報収集と利活用、薬事委員会事務局、疑義照会受付窓口 |
- 病棟業務担当(中央業務担当と兼任)
各業務担当(主任・技師)の職員からなる病棟担当グループ(4~5名)を3班編成し、1グループが4か所程度の病棟を担当しています。 - チーム医療(中央業務担当と兼任)
業務ローテーションと人材育成
小児医療センターの薬剤部では、夜勤と休日日勤を交代勤務で実施しているため、定期的に担当業務の交代を行い、入職の初期から幅広い業務を行える人材育成を目指しています。
人材育成の方法は担当業務でのOJT(On the Job Training)を基本としますが、その期間は職員の業務経験年数や薬剤部の運営方針により異なります。
| 時期 | 到達目標 |
| 採用後3か月 | 職場の環境に慣れ、夜勤業務ができるよう準備をする |
| 6~12か月 | 調剤業務と注射業務の定例業務を全般的に経験する |
| 2年目~3年 |
定例業務ローテーションと病棟担当チームに参加する 薬剤業務を総合的に理解し、自立した業務遂行を目指す |
| 4年目以降 |
小児薬物療法認定薬剤師研修会に参加し、認定取得を目指す 病棟担当チームで主体的に活動する |
| 7年目以降 | 専門的な領域を深める |
調剤業務


調剤室では、処方せんにもとづき内服薬や外用薬、経口栄養剤などの調剤を行っています。
調剤の正確さだけでなく、年齢や発達段階に応じた小児患者が服用しやすい剤形での調剤が求められます。
小児患者が服用する剤形は主に散剤や液剤ですが、流通しているすべての医薬品に小児に適した剤形が存在するわけではありません。このため小児患者の調剤では、錠剤をつぶして散剤にしたり、液剤に変更したりすることがよくあります。
錠剤をつぶして調剤する場合には、複数の工程が必要で時間がかかります。また、本来の剤形を変更する調剤には、作業工程や調剤後の保管に注意が必要です。一方で、流通している散剤や液剤等の小児用剤形は少しずつ増えているため、積極的に採用して安全かつ効果的に薬物療法が行えるよう努めています。
2024年には、自動秤量散薬分包機(調剤ロボット)を2台導入して散薬調剤業務を効率化し、薬剤師の活躍の場を病棟へ広げています。非薬剤師やSPDの方々の力を積極的に取り入れて調剤室業務のタスクシフトを進めながら、患者のみなさまに安全なお薬をお届けしています。
注射薬業務



注射薬室では注射薬個人払出業務、医薬品購入管理業務を担当しています。
注射薬は注射薬自動払出装置を導入して、患者さんごとに一施用単位で供給を行っています。調剤された注射薬は、注射カートに患者さんごとにセットして、薬剤部から各病棟へ搬送しています。
注射薬調剤では、年齢や体重・対表面積に応じた投与量、配合変化や投与速度、併用薬、溶解方法、希釈手順、投与ルートなどが適切に選択されているか薬剤師が確認して、必要に応じて医師に疑義照会を行い、安全に最良の薬物治療を提供できるように努めています。
薬剤師補助業務としてSPD(院内物流管理)や非薬剤師スタッフと協力しながら注射薬室業務のタスクシフトを進めています。SPDに医薬品の期限チェックや棚付け、配置薬補充、注射薬自動払出装置への薬品補充、注射薬搬送業務を委託することで、薬剤師が専門性の高い業務に集中できています。
医薬品の購入管理では約1,300品目の医薬品購入と在庫管理を行っています。小児病院という特殊性を反映して、一般の病院ではあまり見かけない医薬品も多く取り扱っています。高額な医薬品も多く、患者さんに適切に投与できるように細心の注意を払って管理しています。高額な冷蔵医薬品については、トレーサビリティ管理システムを導入して、廃棄リスクの低減と管理業務の効率化を図っています。
無菌製剤業務



無菌室では、院内製剤と注射薬の無菌製剤処理業務(ミキシング)を行っています。
1)院内製剤(無菌製剤)
市販の医薬品だけではすべての疾患の治療に対応できないため、院内専用の「くすり」(院内製剤)を調製することがあります。当センターの院内製剤には、小児患者に適した剤型や特定の診療科との協力で実現した独自の処方があります。
2)無菌製剤処理業務(ミキシング)
薬剤部での無菌製剤処理(ミキシング)業務には、中心静脈栄養輸液(以下、IVH)調製と抗がん薬調製の2種類があり、若手(2~3年目)職員を含むほとんどの職員が調製業務を行えるよう教育しています。
IVH調製
調製者はIVH専用の陽圧クリーンルーム(ISO6)内でミキシングを行っています。小児のIVHは少量の薬剤を何種類も混合することが特徴で、配合変化や安定性について入念な確認を行っています。成人を対象とした病院ではキット製剤が主流ですが、小児輸液ではキット製剤で対応しきれない少量のミキシングが多く、アンプル製剤を用いた細かな操作も多く存在します。また配合変化や安定性だけでなく、患者さんの体重や病態を考慮して、処方内容を確認した上で最良の薬物治療を提供できるように努めています。
抗がん薬調製
調製者は個人防護具(PPE)を着用し、陰圧管理されたハザードルーム(ISO7)の安全キャビネット内でミキシングを行います。抗がん薬調製業務は閉鎖式薬剤移送システム(CSTD)を用いて調製することで、調製者及び院内スタッフへの抗がん薬曝露を防いでいて、患者さんや職員の安全面にも配慮しております。また小児患者に投与する抗がん薬は少量の場合が多いため、重量監査システムを導入しており、1mLに満たない用量の調製も正確に行うことが可能となっています。
また、患者さんの治療に応じたレジメンや、抗がん薬の種類に応じた投与量、投与間隔、支持療法などを入念に確認する必要があるため様々な知識を身につけていくことができます。
医薬品情報業務
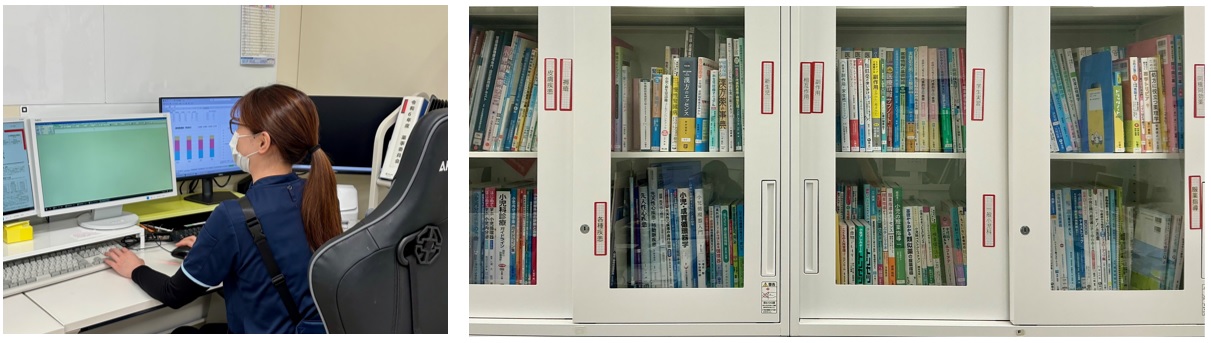
当センター薬剤部では、小児医療における薬物療法の安全性と有効性を確保するため、医薬品情報の収集・整理・評価を行い、医療スタッフや患者さんへ適切な情報を提供しています。
小児領域では、成人に比べて医薬品の適応や投与量に関する十分なデータが得られていないことが多く、科学的根拠(エビデンス)に基づく適正使用が求められます。そのため、国内外のガイドライン、臨床研究、最新の学術論文などを精査し、医療現場での判断に資する情報を提供しています。さらに、PubMed、医中誌Web、UpToDate、ClinicalKey、Ovidなど、国内外の多様な医療データベースを活用し、最新の医薬品情報や治療ガイドラインを迅速に取得・分析しています。また、医薬品の安全性情報(副作用や相互作用を含む)を継続的に収集・分析し、リスクマネジメントの観点から医療チームを支援しています。
医師や看護師からの医薬品に関する問い合わせに、専門的な知見をもとに迅速かつ丁寧に対応し、薬物療法に関する疑問や不安に対し、適切な情報を提供することで、安全で効果的な治療を支援しています。疑義照会や投与設計の相談、投与経路の適正評価など、臨床現場で求められる薬学的介入を積極的に行い、医療スタッフとの連携を強化しています。
薬事委員会の事務局として、医薬品の採用・削除に関する審議を支援しています。各診療科からの医薬品採用申請に対し、薬物動態、臨床試験データ、小児適応の有無、適切な添加物が使用されているか、などを総合的に整理・分析し、科学的根拠と医療経済的視点を踏まえた情報を提供することで、委員の適正な判断をサポートしています。また、ワクチンや予防医療に関する最新の情報を収集・提供し、感染症予防や公衆衛生の向上に寄与することも重要な役割の一つです。ワクチンの有効性や安全性に関するデータの分析、接種スケジュールに関する助言を行い、医療スタッフが適切な判断を下せるよう支援するなど、医薬品の適正使用推進に向け、医師・看護師をはじめとする多職種と連携し、小児医療における薬物療法の質の向上に貢献しています。
試験検査業務
試験検査室では、抗菌薬の効果を最大限かつ副作用の発現を最小限にするために、TDM(薬物治療モニタリング)を行っています。
小児においては、画一的な投与量では至適血中濃度のコントロールが困難な事例が多数あります。腎機能低下、循環動態不安定、透析治療を受けている場合は、特に集中的な管理が必要です。各診療科の医師と情報共有を行いながら、効果や副作用に関する因子を継続的に確認して、患者ごとに個別化した投与設計を行っています。
小児の薬物投与設計では難しい場面が多々ありますが、提案した治療計画をもとに患者の病態が改善したときは、とても大きな達成感を得られます。
病棟薬剤業務・薬剤管理指導業務
現在、集中治療病棟と小児がん病棟、循環器科病棟など5か所の病棟と手術室で病棟薬剤業務を実施しています。今後すべての病棟に薬剤師を配置する計画があり、小児薬物療法の安全確保と適正化に貢献できるよう、各診療科や関係部門と連携して、小児病院に望まれる病棟薬剤業務・薬剤管理指導業務を模索しているところです。
チーム医療
ICT/AST(感染制御チーム:Infection Control Team / 抗菌薬適正使用支援チーム:Antimicrobial Stewardship Team)
ICT/ASTチームでは週1回カンファレンスとラウンドを行っています。
カンファレンスでは1週間で特定抗菌薬(より適切に管理が必要な抗菌薬)を使用した患者について共有し、使用目的や使用期間が適切であるかディスカッションを行います。
ラウンドでは病棟と各セクションを視察し、衛生管理が適正に行われているか確認を行います。
また月1回のICT会議や感染防止委員会で、抗菌薬に関する情報を院内向けに発信しています。
NST(栄養サポートチーム:Nutrition Support Team)
NSTでは週1回カンファレンス(カルテ回診)を行い、依頼があった患者の栄養管理について話し合っています。
カルテ回診後は実際に病棟を訪問して患者の状態を確認し、長期入院のため栄養状態の悪化が懸念される患者の栄養摂取状況の確認を行っています。
薬剤師は、患者に投与されている静脈栄養や栄養管理に影響を及ぼす薬剤について確認しています。小児では、患者の成長を考慮した栄養管理を行うこと、ミルクや経腸栄養剤の内容によっては不足する栄養素があるため、モニタリングと補充を行うことなどが特徴です。
また、月1回のNST委員会では回診状況の確認や、栄養管理に関する院内勉強会についての企画を行っています。
この他、PCT(緩和ケアチーム)や褥瘡管理チームの活動にも薬剤師が参加しています。
その他の業務(実務実習、他施設や地域との連携)
実務実習の受入
病院実務実習で薬学生の受入を行っています。
| 第Ⅰ期 | 第Ⅱ期 | 第Ⅲ期 | 第Ⅳ期 |
| ― | 4※ | 4※ | 4※ |
他施設や地域との連携
- JACHRI(一社・日本小児総合医療施設協議会:https://jachri.or.jp/)
全国の小児専門病院が集まり、小児医療に固有の課題を共有するとともに、小児医療の充実と発展について国等に働きかける活動を行っています。 - さいたま市薬剤師会・さいたま地域連携Network
さいたま市地域の薬薬連携の一環として、研修会の開催や院外処方箋の疑義照会プロトコルを締結しています。
また、さいたま市版おくすり手帳の開発プロジェクトも進行しています。
薬剤部のお仕事紹介(YouTube動画)について
「このお薬、どうやって作っているんだろう?」そんなふとした疑問をお持ちのかたもいらっしゃるかもしれません。
患者さんのもとに届くお薬が、どのように作られているのか、当センターの薬剤師が紹介しています。
埼玉県立小児医療センター公式YouTubeチャンネル「おくすりの舞台裏~薬剤部のお仕事紹介~」
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください