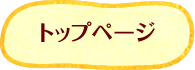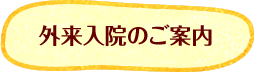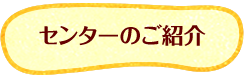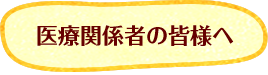埼玉県立 小児医療センター > 各部門の紹介 > 内科系診療部門 > 遺伝科 > FAQ(よくあるご質問) > 福祉について
ここから本文です。
掲載日:2024年7月8日
福祉について
福祉について(質問)
- (Q1) 親の会は参加した方がいいですか?
- (Q2) 特別児童扶養手当はいつから申請できますか?
- (Q3) 特別児童扶養手当と障害児福祉手当の違いは何ですか?
- (Q4) 手帳を取得することのメリットを教えてください。
- (Q5) 手帳は何歳から申請できますか?
- (Q6) 保育園に入りたいのですがどこに相談したらいいですか?
福祉について(回答)
Q1 親の会は参加した方がいいですか?
様々な情報も集まりますし、お友達もできるので、参加することのメリットは大きいです。しかしながら、親の会も様々で会によっての特徴もあります。ご家族、お子さん自身との相性もありますので、まずはお試しで連絡を取ってみて、会の様子を聞いてみることから始めてみてはいかがでしょうか。また、遺伝科や相談支援センターでは親の会の発行物を閲覧していただくこともできますので、お声かけください。
Q2 特別児童扶養手当はいつから申請できますか?
発達の遅れで申請する場合は、1歳を過ぎた頃に遺伝科受診時に医師より案内しています。疾患の状況によってはそれ以前でも申請が可能な場合がありますので、主治医やソーシャルワーカーにご相談ください。
Q3 特別児童扶養手当と障害児福祉手当の違いは何ですか?
特別児童扶養手当はその児童を扶養する者(保護者)が受け取り、障害児福祉手当はその児童本人が受け取るものです。また、それぞれの支給基準も異なります。詳しくは市区町村の担当課かソーシャルワーカーにお問合せください。
Q4 手帳を取得することのメリットを教えてください。
取得した手帳の種別や等級、お住いの地域によって手帳取得により受けられるサービスは異なりますが、補装具や日常生活用具の購入費用の助成、税金の控除、公共交通機関・施設の利用料金の減額などを受けることができます。詳しくは市区町村の担当課かソーシャルワーカーにお問合せください。
Q5 手帳は何歳から申請できますか?
療育手帳
年齢制限はありませんが、1歳前の幼少時に申請した場合、判定がつかず、非該当になる場合があるようです。ダウン症のお子さんの場合は1歳過ぎ頃がおおよその目安のようですが、お子さんの発達状況によってはその時期でも非該当になる場合があります。お子さんの発達の状況を見ながら、申請時期を検討してください。
身体障害者手帳
各障害の基準に該当すれば申請可能です。ただし、各障害によって申請年齢におおよその指針が出されている場合がありますので、申請を希望する場合は主治医やソーシャルワーカーにご相談ください。
Q6 保育園に入りたいのですがどこに相談したらいいですか?
市区町村によって、障害児枠を設けている場合、特にない場合、加配(職員を増やす)制度を利用できる場合など様々です。年度途中からの利用の場合は特に入所が難しくなる傾向がありますので、早めにお住いの市区町村の保育課等にご相談を始めてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください