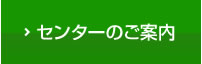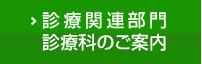埼玉県立がんセンター > 診察関連部門・診察科のご案内 > 診療関連部門のご案内 > 緩和ケアセンター(緩和ケアチーム/緩和ケア病棟) > 緩和ケアチーム > 症状について
ここから本文です。
掲載日:2025年8月26日
症状について
よくみられる症状
痛み
がんの患者さんの8割で痛みを生じるといわれています。2割の患者さんは痛みはありません。また痛みは他の症状と比べて、早いうちから生じることも多いです。しかし、痛みのある患者さんのほとんどは医療用麻薬を中心とした鎮痛薬でを痛みを取り除くことができます。
痛みはがまんしたほうが良いのですか?
痛みにかぎらず、症状はできるだけがまんせずに緩和するほうが体への負担も少なくてすみます。痛みをがまんしていると、夜眠れなくなり、そのために昼間にだるくなったり、眠くなったり、食欲が落ちたりして、体が弱っていきます。また、症状が軽いうちは、外来で薬の調整をして自宅で様子をみていくことができますが、症状を限界までがまんしてから薬を調整しても、すぐには効果が出ないために入院が必要となってしまうことがあります。「がまんしないこと」は、できるだけ入院せずに自宅で過ごすために大事なことなのです。
モルヒネは最後の薬ですか?
モルヒネなどの医療用麻薬※には多くの誤解があるようです。多くのがんの患者さんが医療用麻薬を上手に使いながら日常生活を送っています。
医療用麻薬は「最後に使う薬」と思われがちです。最初から強い薬を使うと後で痛くなった時に効かなくなるのではと心配されるかと思いますが、そのようなことはありません。逆に、最後まで使わないようにと考えて、ぎりぎりまでがまんしてから、これらの薬を使う場合、最初から薬を多く使うわけにはいきませんので、なかなか痛みがとれないことがあります。まだ痛みが軽いうちから、医療用麻薬を徐々に使っていくことが、上手に痛みと付き合うコツです。
※医療用麻薬:現在使用されている医療用麻薬には、モルヒネ(オプソ、モルヒネ塩酸塩、モルヒネ硫酸塩徐放細粒など)、オキシコドン(オキノーム散、オキシコドン徐放錠など)、フェンタニル(フェントステープ、イーフェンバッカル錠など)、ヒドロモルフォン(ナルラピド、ナルサスなど)の、主に4種類の薬があります。
モルヒネで胃が荒れませんか?
モルヒネなどの医療用麻薬には胃が荒れるといった副作用はありません。そのため、食事とは関係なく空腹時に内服していただいても全く問題がありません。むしろ、軽い痛み止めと考えられている消炎鎮痛薬(ロキソプロフェン、ジクロフェナク坐剤など)の方が、実は胃潰瘍や腎障害といった副作用があります。医療用麻薬の良いところは、少ない量から始めて徐々に増やしていけば、副作用が少ないところです。
モルヒネを使うと命が縮む?
モルヒネなどの医療用麻薬を使った場合と使わない場合では、寿命に変わりがないということが研究でわかっています。むしろ、痛みをがまんしていると夜眠れなくなり、そのために昼間にだるくなったり、眠くなったり、食欲が落ちたりして、体が弱っていくことが多いように思います。
息切れ、息苦しさ、せき
原因はさまざまですが、半分以上の患者さんで生じる症状です。酸素が足りなくなるような患者さんでは、酸素を吸う方法もあります。在宅酸素療法といって、自宅でも行うことができます。また、息切れ、息苦しさ、せきに対しても、モルヒネなどの医療用麻薬は効果があります。せきに対しては、薬局などで売られているせき止めに比べて効果があります。
食欲低下
食欲の低下は多くの患者さんでみられます。
便秘
便秘はがんの患者さんで多くみられる症状です。普段どおりの排便ができるように下剤の調整が必要になります。もともと1日1回排便がある方はそれを目標とします。排便のない日数が長くなればなるほど、便は硬くなり、出にくくなりますので、早めの対策が必要です。また、便の回数だけでなく、便の量やかたさも注意してみていきましょう。毎日、あるいは、トイレに行くたびに少しずつ下痢便がある場合には宿便の可能性も考えなければいけません。宿便になると、硬い便が腸の中に残っていて、まわりの軟らかい便だけが出てくる状態です。この場合、毎日排便があったとしても安心はできません。場合によっては浣腸などで腸の中の硬い便を出してしまわなければならないこともあります。そのような症状が続く場合には担当医師と相談してみましょう。
むくみ
特に足のむくみは多くのがん患者さんにみられます。むくみが出てくると不安に感じる方も多いと思いますが、すぐに対処しなければいけないことはほとんどありません。むくみの原因は、がんがあると、どうしても血管やリンパ管から水分がしみ出やすくなるためと考えられています。むくみがあっても患者さんが苦痛と感じていなければ、特別な対処は必要ありません。むくみのために足が重い、だるいなどの苦痛がある場合には、圧迫療法や利尿剤(尿を増やす薬剤)で対処することもあります。
夜眠れない
多くの患者さんで夜眠れない(不眠症)が生じます。原因はさまざまですが、病状についての不安などが原因ということも多いようです。不眠症になると、疲れやすくなったり、日中うとうとしてしまったり、さらには昼と夜が逆転して、日中に眠って、夜起きているというパターンになってしまうことがあります。心身ともにすこやかな生活には、眠りは何より大切です。ぐっすり眠ることができれば、翌朝には心身ともにすっきりすることができます。床に就く前には、静かな音楽を聞いたり、好きな香りを楽しんだり、お風呂に入ったり、リラックスすることが安眠につながります。どうしても眠ることができないことが続くようであれば、睡眠薬を使う方法があります。睡眠薬はクセになるので、できるだけ使わないほうが良いと考える方も多いようです。しかし、がんのように休息が必要な病気では睡眠薬を使って、夜に十分な休息をとることは重要です。睡眠薬は何種類もありますので、不眠の状況によって担当医師と相談して選ぶとよいでしょう。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください