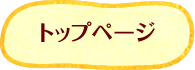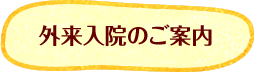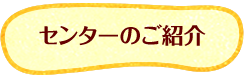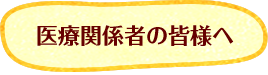埼玉県立 小児医療センター > 医療関係者の皆様へ > 保険薬局の方へ【院外処方せんの疑義照会等】
ここから本文です。
掲載日:2025年7月31日
保険薬局の方へ【院外処方せんの疑義照会等】
埼玉県立小児医療センターでは、院外処方せんの疑義照会(薬物療法に関することに限る)は薬剤部が窓口になっています。薬剤部では院内プロトコルにしたがい、カルテの確認や医師への連絡など、いくつかの手順を経てから回答しているため、内容によっては時間を要することがあります。
なお、患者さんの保険者番号や公費負担番号など、診療報酬や費用負担に関する事項は、薬剤部では回答できませんので、医事担当にお問合せください。
電話番号:048-601-2200(代表)▶薬剤部医薬品情報室
平日の 9時~12時、13時~17時
担当者が対応中の時は電話がつながらないことがあります。
この場合は回線の混雑防止のため、いちど電話を切り、しばらくしてからかけ直してください。
また、夜間・休日は担当者が不在のため、緊急時(調剤過誤や有害事象の発見など)を除き、上記の時間帯に連絡してください。
保険薬局から薬剤部に寄せられる照会のうち、よくある質問について掲載します。なお、内容の無断転載または引用はご遠慮ください。
1.院外処方せんに関した出来事の報告依頼について
当センター発行の院外処方せんに関して発生したインシデント・アクシデントのうち、以下の事象については、患者さんの治療に重大な影響を与えるおそれがありますので、直ちに電話連絡をしてください。また速やかに、詳細な情報を書面(ファックス)で報告をしてください。
電話番号:048-601-2200(代表)▶薬剤部医薬品情報室
(1)報告が必要な事象(電話で概要を、書面で詳細を報告してください)
(ア)重大な副作用が疑われる場合
(イ)著しい服薬不遵守、あるいは誤用が疑われる場合
(ウ)医薬品の不良など、患者から苦情や相談を受けた場合
(エ)調剤過誤が発生した場合
(オ)上記以外で報告が必要と判断された場合
(2)書面での報告事項と様式
様式は任意ですが、以下の事項は必須とします。
(A)事象の分類(上記の(ア)~(オ)の区分、特に(オ)の場合は具体的な事項を記入)
(B)発生日(発見日)
(C)患者名(患者番号)
(D)患者の状態
(E)発生の経緯(時系列で報告してください)
(F)対策(再発防止策)
(G)報告者の連絡先
(3)書面での報告方法
郵送もしくはファックスで報告してください。
郵送の場合
〒330-8777
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地2
埼玉県立小児医療センター薬剤部 宛
ファックスの場合
ファックス番号(048-601-2201)ではなく、下記の番号に送信してください。
ファックス番号:048-601-2213(薬剤部直通)
(4)インシデント・アクシデント共有事例
これまでに集積された報告のうち、小児病院の院外処方せんに特徴的な事象を取りまとめましたので、共有をお願いします。
2.院外処方について
(1)院外処方せんでオーダ可能な医薬品について
以下の一覧表に掲載した医薬品は、院外処方せんでオーダ可能な医薬品として医療情報システムにマスタ登録されているものです。
一覧表には、病院で採用している医薬品(院内採用薬)だけでなく、院外処方用としてオーダ可能な医薬品(院外限定薬)も含まれています。また、在宅医療用として一部の輸液類も掲載しています。
当センターは小児専門病院のため、小児用剤形を中心に複数の規格・剤形の医薬品を採用しています。後発医薬品の採用を推進していますが、小児適応の有無や製剤上の優位性から特定の銘柄を採用している場合もあります。また、病院の特性から稀少疾患治療薬など、流通面で制限のある医薬品も採用しています。このため医薬品の在庫確保および調剤の際にはご留意ください。
(2)医薬品の投与量について
一般的に、小児薬用量は患者さんの体重や体表面積をもとに決定され、これに患者さんの代謝・排泄機能や症状に応じた補正が加わります。また、患者さんの年齢や発達段階に応じて最適な剤形が選択されますが、適当な剤形や規格が存在しない場合は、錠剤粉砕や脱カプセル等で対応する必要があります。
このように、小児病院では多様な年齢と発達段階の患者さんに応じた薬物療法を提供する必要があるため、多規格・多剤形の医薬品を採用しています。
したがって、薬物療法の指示を行う際には、剤形や規格の違いに関わらず、投与量を明確に把握できるよう、成分量(mgなど)で表記することを原則としています。
例えば、処方せんに記載されている倍散等の名称のあとに「力価」とある場合は成分量での表記であり、「重さで」とある場合は製剤量での表記となります。これは処方せんだけでなく、院内処方の「処方せん控え」や「おくすり手帳シール」についても同様です。
この部分は、多くの調剤薬局がレセプトデータにもとづいて製剤量(薬価請求単位)で表記している場合と異なりますので、ご注意ください。
(3)後発医薬品への変更について
当センターに後発医薬品への変更等を報告していただく場合は、病院のファックス番号(048-601-2201)ではなく、以下の薬剤部直通ファックス番号へお願いします。
ファックスの送信登録先が薬剤部直通番号でない場合は、お手数でも再設定をお願いします。
ファックス番号:048-601-2213(薬剤部直通)
(4)院外処方せんを応需する際の対応について
当センターを受診される患者さんは、複数の診療科を受診する場合が多いことから、かかりつけ薬局での調剤を推奨しています。院外処方せんによる調剤を応需される際には、疾患や発達段階などを含め、患者さんとご家族の背景に十分配慮した対応をお願いします。
埼玉県立病院機構では電子処方せんへの対応を2段階で進めています。
Step.1【2025年3月11日から】電子処方せん管理サービスに処方情報を登録
マイナポータルでの重複投与の確認やオンライン資格での調剤結果の参照のみ
これまでどおり紙の院外処方せんが原本です。
Step.2【令和10年(2028年)頃】電子カルテシステムの更新時期に合わせて電子処方せんに移行
小児医療センターは令和10年度(2028年)に移行を予定しています。
さいたま市薬剤師会が運営しているファックスの保守サポートが終了することを受け、令和8年(2026年)2月27日(金曜日)で院外処方せんのファックス送信を終了します。
ファックス送信の終了にともない、処方せんの事前送信はスマートフォン等のお薬手帳アプリを利用した画像送信機能で代替します。
これまで事前にファックスで処方せんを送信していた患者さんについては、アプリ等による処方せん画像の送信機能について、ご案内いただきますようお願いいたします。
3.疑義照会簡素化プロトコルについて
院外処方せんの疑義照会にかかる問い合わせ業務と調剤手順を簡素化するために、院内の申し合わせ事項を集約して疑義照会簡素化プロトコルを作成しました。
このプロトコルは、令和3年2月にさいたま市薬剤師会と合意書を締結しています。このため、さいたま市薬剤師会に加盟する調剤薬局では、プロトコルにもとづいた疑義照会事項は問い合わせを不要としています。処方箋または調剤録に「埼玉県立小児医療センター疑義照会簡素化プロトコルの合意による変更」と記載し、合意による変更である旨を明記するとともに、事後に服薬情報提供書<様式G-1>にて報告してください。
- 報告先:048-601-2213(薬剤部専用ファックス番号)
- 服薬情報提供書<さいたま市薬剤師会:様式G-1>(PDF:93KB)
なお、他の地域の調剤薬局においても、このプロトコルに同意いただける場合については、問い合わせを不要とします。その際にはさいたま市薬剤師会との合意に準じ、処方箋または調剤録に「埼玉県立小児医療センター疑義照会簡素化プロトコルの合意による変更」と記載し、合意による変更である旨を明記するとともに、事後に報告してください。
- 報告先:048-601-2213(薬剤部専用ファックス番号)
- 服薬情報提供書<汎用様式>(PDF:94KB)
4.当センターの内服薬調剤方法
(1)散剤の賦形量について
当センターでは令和6年度に自動散薬分包機(調剤ロボット)を導入しました。
これにともない、自動散薬分包機と薬剤師による計量では散薬賦形の手順が異なることがあります。散薬計量時の賦形手順については、以下の散薬賦形の基準にしたがっていますので、参考にしてください。
なお、調剤薬局での賦形手順が当センターと異なる場合は、患者さんが不安に感じられることがありますので、十分に説明していただくようお願いいたします。
(2)内用水剤の賦形について
当センターでは内用水剤の賦形は行っておりません。
(3)錠剤の粉砕・脱カプセルについて
1錠(または1カプセル)の重さを以下のように設定し、処方された用量分の重さを計算して量りとっています。
- 素錠:添付文書記載の重さ
- フィルムコート錠:粉砕して300μmのふるいで篩過した重さ
- カプセル剤:カプセルを外したときの中身の重さ
粉砕した薬剤の長期安定性が保証されない場合は、分割調剤で対応していただくようご協力をお願いいたします。
5.よくある質問
Q.処方せんの指示と「異なる規格」または、「異なる剤形」の薬剤で調剤していいですか?
A.当センターにご連絡ください。基本的には患者さんの了解が得られれば良いです。患者さんに十分説明してください。
Q.処方せんの指示と「異なるメーカーの薬剤」で調剤していいですか?
A.後発医薬品変更不可になっていなければ、後発医薬品への変更は問題ありません。それ以外の場合は当センターにご連絡ください。
Q.散剤の賦形量について教えてください。
A.年齢と用法で賦形量を決定しています。詳細については、散薬賦形の基準_20250109(PDF:360KB)を参照してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください